金の菊芋 菊芋 ( きくいも ) 血糖値 が高く血糖コントロールや調整に四苦八苦している人に 菊芋 はおすすめです。どのような理由からおすすめかを紹介します。血糖値、ヘモグロビンA1Cが気になっている方は一度試してみてください。菊芋は、血糖を下げる成分がたっぷり含まれることから注目の食材です。
その成分とは、イヌリンと呼ばれる成分が多く含まれているのが特徴です。 イヌリンはお腹が空きにくくなる、血糖値の上昇を抑制するなどの効果があることから、糖尿病やダイエットに効果大です。
金の菊芋 血糖値 が高く安定しない人ほど食べた方がいい

糖尿病とは、血液中の糖が過剰になった状態が続く病気です。放置したままにすると、全身を巡る血管がボロボロになり、その影響から合併症へと進展していきます。
糖尿病と診断された時点ではほとんどの人は自覚症状がないために生活習慣、食習慣を変えるための自覚がありません。早期治療を開始すれば予後は明るいのですが、放置期間が長期化すればするほど予後は非常に悪い です。
医師の中には、糖尿病は、血管の病気だと言う方も多数いらっしゃいます。糖尿病による合併症は血管の病気から始まります。
しかし、糖尿病と診断された方には、生活習慣の改善や食習慣の改善が必須となります。その一方で、食事や生活は毎日のことなので、食事制限や運動療法などの厳しい条件を守らなければならないつらさも理解できます。
好きなものを自由に食べていた人にとって、食事制限は大変つらいものです。あれもこれも食べてはダメという指導ではなく、「積極的に食べて血糖値を下げることができる食材はないものか多くの方が研究しています。
そんなとき発見されたのが 「 菊芋」 というキク科ヒマワリ属の多年性植物です。生で食べると大根のような食感で、甘みがあります。さまざまな料理にも幅広く活用できます。見た目は生姜と似ているので間違えてしまう人もいます。
「 菊芋 」 が血糖値を下げる最大の理由は、イヌリンを豊富に含んでいること。イモ類の糖質はデンプンであるのに対して、「キクイモ」の糖質は多糖類の一種であるイヌリンです。
デンプンは体内に吸収されるとすぐにブドウ糖に分解されて血糖値を上昇させますが、約30もの果糖が長くつながって構成されているイヌリンの場合は、分解されても短い果糖になるだけで、消化されにくく血糖値の上昇を穏やかにしてくれるのです。つまり、菊芋は、血糖値を上げずに体内のエネルギーを補給する効果があります。
ドクターらが試した実験で菊芋の焼酎を飲みながらの食事で揚げ物や麺類などの炭水化物をたっぷりとったにもかかわらず食後血糖値が大幅に下がったデータもあります。芋という名前がイメージ的に糖質をイメージしてしまいますが、まったく芋とは異なるものなのです。
血糖値 ヘモグロビンA1C 高い人 数値の悪い人ほど効果がでやすい
実際に菊芋の効果ですが、数値の悪い人ほど大きく改善する傾向があります。ひとつの症例ですが、72歳女性です。ヘモグロビンA1Cは、10.1 % もあり非常に悪い状態でした。入院をすすめられたのですが、近々友人らと温泉旅行があるから入院しないというのです。
温泉旅行に行けば、間違いなく贅沢な食事でもっと数値が上がることは容易に想像できましたが、やめさせるわけにもいかず、しぶしぶ許可を出しました。代わりに、血糖値を下げる飲み薬を処方し、食前に 「 菊芋 」 のお茶をとることをすすめたのです。
最近は、菊芋のパウダーが売られているのでお湯をかければ菊芋ティーのできあがりです。簡単ですから誰でも取り入れることができます。
すると、その翌月の検査数値から血糖値とヘモグロビンA1Cの数値が着実に下がり始めました。4ヶ月足らずでヘモグロビンA1Cが4.3%も下がったのですから驚きです。薬との相乗効果だったとは思いますが、効果はかなり強力だと思いました。
イヌリンは食前に摂るとより効果的 食物繊維(イヌリン)の働き
水溶性の食物繊維「イヌリン」を豊富に含んでいる。イヌリンは難消化性で消化に時間がかかるため、胃腸内に長時間とどまります。腸管内での糖の吸収をゆるやかにし、インスリンの無駄遣いを減らして血糖値の急上昇を抑えます。食事前に摂るようにすればより効果的です。
ミネラル
菊芋 からは、カリウム、ナトリウム、マグネシウム、カルシウム、リン、鉄、マンガン、銅、亜鉛、セレンが摂取できます。糖尿病患者はミネラルが不足して、インスリンの分泌が低下しやすいので 菊芋 で補うことができます。
ビタミン
糖尿病の人に特に重要な3つのどタミンがとれます。不足すると血糖値が上がるため、糖尿病患者に不可欠などタミンB1、免疫を正常に機能させるどタミンB2、糖尿病合併症の血管障害にも有効などタミンCが含まれています。
血圧降下作用も 血圧が高い人にも効果がある
菊芋 は、血糖値やヘモグロビンA1Cを下げるだけでなく血圧を下げる作用もわかってきました。血圧を下げるのもやはり 食物繊維のイヌリン です。
- 菊芋に豊富に含まれるイヌリンは、水溶性食物繊維の一種です。イヌリンは、腸内細菌によって分解されると、短鎖脂肪酸という物質が生成されます。短鎖脂肪酸には、血圧を下げる作用があることが知られています。
- 菊芋には、カリウムも豊富に含まれています。カリウムには、ナトリウムを排泄する作用があり、血圧を下げる効果があります。
『 金の菊芋 』 食後の血糖値の上昇を抑える! 機能性表示食品
金の菊芋|天然イヌリンたっぷり 食後の血糖値が気になる方へおすすめ菊芋サプリです。
金の菊芋 は、菊芋 ( きくいも ) そのものを1粒に凝縮したサプリメント。菊芋に含まれている水溶性食物繊維「イヌリン」には、食後の血糖値の上昇を抑える機能が報告されており、その効果は臨床実験でも実証済み。
食後の血糖値が気になる方へおすすめです。さらに菊芋の純度にもこだわりました。金の菊芋は独自技術により、主成分の菊芋を99%も含ませることに成功。菊芋の驚くべきパワーをまるごとサプリにしています。
1 日 7 粒を目安に食前にお召し上がりください。そのまま噛んでいただくか、お水などと一緒にお召し上がりいただけます。
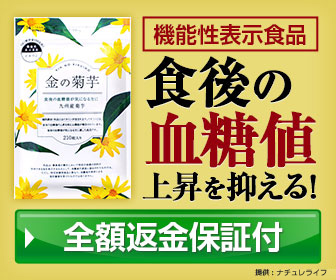

【機能性表示食品】金の菊芋サプリメント 
- 名称
- 菊芋加工食品
- 原材料名
- 菊芋(九州産)、ステアリン酸カルシウム
- 内容量
- 52.5 g ( 250 mg × 210 粒)
- 商品タイプ
- >粒状(キクイモタブレット)
- 使用方法
- 1日7粒を目安に食前にお召し上がりください。そのまま噛んでいただくか、お水などと一緒にお召し上がりいただけます。
- 機能性関与成分名
- イヌリン
- 届出表示
- 本品にはイヌリンが含まれます。イヌリンには、食後の血糖値の上昇を抑える機能が報告されています。食後の血糖値が気になる方に適した食品です。
- 注意事項
- 本商品は固いためお召し上がりの際、歯の弱い方はご注意ください。製品表面に白いかたまりや小さな黒点・茶色い点がみられることもありますが、使用されている原料由来のものですので品質に問題ありません。
サプリメントはうさんくさいと思っているあなたに 菊芋 パウダー がおすすめ
菊芋 パウダー 国産(長野県産)100%のキクイモの粉
粉末だからお茶だけでなく飲み物や料理に混ぜ合わせて簡単に摂取できます。食前に摂るのが効果的ですが、食前にお茶で1杯飲み、食事中にもお味噌汁などに入れて飲むとさらに効果アップです。ヨーグルトなどに混ぜて食べるのが人気です。
菊芋パウダーで血糖値の上昇を防ぐことができます。味にはクセがないのでお湯に溶いてお茶がわりに飲んでも全く問題ありません。水分制限がある方は、ご飯などにまぜて食べてもいいでしょう。
[PR] [PR]
リンク
菊芋 ( きくいも / キクイモ ) 使用感



